人の定義は未定である
人間の定義は多岐にわたり、どの側面を重視するかによってその内容は大きく異なります。生物学的な分類から法的な権利、さらには哲学的な自己認識や社会的な役割まで、様々な視点から人間を理解しようと定義つけの試みがされています。
明確な定義はなぜ必要か
Table of Contents(コンテンツ目次)
 何かについて考え主張し説明する時に、あなたが伝えようとする言葉をかみ砕いた文章を用意しておくこと、すなわち文章化が必要です。テーマの「人の定義」の前に言語化、文章化の違いの定義を例示します。
何かについて考え主張し説明する時に、あなたが伝えようとする言葉をかみ砕いた文章を用意しておくこと、すなわち文章化が必要です。テーマの「人の定義」の前に言語化、文章化の違いの定義を例示します。
言語化:「嬉しい」という感情を「楽しい」「幸せ」「ワクワクする」など言葉(ことば)で表現
文章化:「嬉しい」という感情を「今日はとても嬉しい気分です」という文章(ぶんしょう)で表現する
言語化と文章化の違い
言語化は、話すことも含め、思考や感情を何らかの形で「言葉にする」ことを指します。例えば、「この企画、もっと面白くするにはどうすればいいかな」と口に出すことも言語化です。
一方、文章化は、その「言葉にしたもの」を文字として定着させる(文字起こし)行為です。上の例は、ブレインストーミングの結果をまとめることが文章化に当たります。
文章化は一種の言語化で、「文字による言語化」と捉えることもできます。ブレインストーミングを開始する際に、“では、皆さんここからまず各自のアイデアをポストイットに書いて張り出してください。そして各自のアイデア出しが終わったら……….“とチームリーダーがブレインストーミングの進行をします。
さてアイデアの定義は?
「アイデアの定義」に関するチームミーティング
参加者:
- Alice(プロジェクトマネージャー)
- Sara(マーケティング担当)
- Scott(開発担当)
- Ted(デザイナー)
 対話:
対話:
Alice: 皆さん、お疲れ様です!今日のミーティングは「アイデアの定義」についてですね。普段何気なく使っている「アイデア」という言葉ですが、チーム内で認識を合わせることで、今後のブレインストーミングや企画立案がよりスムーズに進むと考えています。まずは皆さんの考える「アイデア」の定義について、自由に意見を出してください。
Sara: 私は「新しい価値を生み出す、斬新な発想や着想」と捉えています。単なる思いつきではなく、何らかの問題解決やニーズに応えるもの、という点が重要だと感じます。
Scott: そうですね。僕もSaraさんに近いですが、「現状を改善したり、新しい機能やサービスを創造するための具体的な解決策の種」というイメージです。技術的な実現可能性も少しは意識しますね。
Ted: 私はもっと広義に捉えていて、「既存の枠にとらわれず、何かを生み出すためのひらめきや思考の出発点」だと考えています。デザインの現場だと、最初の漠然としたイメージも「アイデア」と呼ぶことが多いです。そこから具体化していくプロセスを含めて、ですね。
Alice: なるほど、皆さんそれぞれ少しずつニュアンスが違いますね。Saraさん、Scottさんは具体的な価値や解決策という点に重きを置いている。Tedさんは思考の出発点やひらめきという、より抽象的な部分も含まれると面白いです。
Alice: では、もう少し深掘りしてみましょうか。例えば、「ただの思いつき」と「アイデア」の違いは何だと思いますか?
Sara: 「ただの思いつき」は、その場でパッと思いつくだけで、検証や実現性や再現性への考慮がないものだと思います。「アイデア」は、そこから一歩踏み込んで、何らかの目的意識や実現への可能性を感じさせるもの、という違いでしょうか。
Scott: 同感です。「ただの思いつき」は、「ああ、あれもいいかもね」で終わってしまう。でも「アイデア」は、「これ、もしかしたら面白いんじゃないか?どうやったらできるかな?」と、思考が先に進むトリガーになるもの、と僕は考えます。
Ted: 私は、「共感を呼ぶ、あるいは議論を促すか」という視点も大きいと思います。「ただの思いつき」は、聞いて終わり。でも「アイデア」は、「それ、いいね!」「それはどうなの?」と、周りを巻き込み、発展していく可能性を秘めているものだと感じます。
Alice: 素晴らしい視点ですね!「検証」「思考のトリガー」「共感を呼ぶ、議論を促す」。これらは「アイデア」を「ただの思いつき」と区別する重要な要素になりそうです。
Alice: では最後に、私たちのチームにとって、どのような「アイデア」を求めているか、という観点で再定義してみませんか?今後のプロジェクトで、皆が「これぞアイデアだ!」と思える共通認識を作りたいです。
Sara: そうですね。だとすれば、「顧客や市場の課題を解決し、新たな価値を創造する、実現可能性のある具体的な発想」というのはどうでしょうか。漠然としすぎず、かつ柔軟性も持たせたいです。
Scott: 僕からは、「技術的な制約を理解しつつも、現状を打破し、イノベーションに繋がるポテンシャルを秘めた、実現に向けた具体的なロードマップを描けるような発想」としたいです。ちょっと長いですか。
Ted: 私は、「ユーザーの心に響き、感動を生み出すような、独創的でかつチームで具現化できるビジョンの種」という表現が良いと思います。デザイン的な側面も加味して。
Alice: 皆さん、ありがとうございます!それぞれの専門性を活かした、非常に具体的な定義が出てきましたね。これらを統合し、私たちのチームの「アイデア」の定義として、次のようにまとめたいと思います。
私たちのチームにおける「アイデア」の定義:
 「顧客や市場の課題を深く理解し、新たな価値を創造する、実現可能性のある具体的な発想の種、源泉。アイデアは単なる思いつきに留まらず、検証や議論を通じてチームを巻き込み、イノベーションへと導くポテンシャルを秘めている。」
「顧客や市場の課題を深く理解し、新たな価値を創造する、実現可能性のある具体的な発想の種、源泉。アイデアは単なる思いつきに留まらず、検証や議論を通じてチームを巻き込み、イノベーションへと導くポテンシャルを秘めている。」
Alice: どうでしょうか?この定義で、今後のブレインストーミングや企画検討の際に、皆で「これはアイデアだ」「いや、まだ深掘りが必要だ」といった共通認識が持てるようになるかと思います。
Sara: 非常に明確で、私たちのアクションに繋がりやすい定義だと思います。
Scott: はい、技術的な視点からも納得感があります。
Ted: デザインの初期段階のひらめきから、具体的な形になるまでのプロセスも包含されていると思います。
Alice: 良かった。この定義をいつも念頭に置いて、悩んだらこの定義に戻り、次のプロジェクトに臨みましょう、ありがとうございました。
全員: ありがとうございました!
かみ砕いた定義:「アイデアとは、個人がそれぞれに持つリアルな体験や経験など既存の情報・要素の新しい組み合わせです。組み合わせ方はいくつかあります。もう一度起こる再現性があることです。ブレインストーミングの参加者が多く、リアルな体験や経験など扱う情報量が多ければ多いほど、良いアイデアに到達する可能性があります。」
さて、ここで日本と西欧、英語圏のコミュニケーションにおける背景、文脈や状況、これらは一語で「コンテクスト」と言います。その共有度合いによって分類される文化のこと。大きく分けてローコンテクストとハイコンテクストです。
日本はハイコンテクスト文化

ハイコンテクストとは?
日本語を含む俳句、和歌はなどの日本文化は「ハイコンテクスト(hi-context)」と言われ、言葉で明確化しにくい背景や文脈から聞き手、読み手の意図をくみ取り、読み取りコミュニケーションをします。
- 場の空気を読んだ発言
- 「大丈夫」と一言あったので、状況から推測して大丈夫の意味を理解したが、
- 相手の発言の意図の推測が間違っていて、ミスコミュニケーションが生まれた。
ローコンテクスト(low-context)
ローコンテクスト(low-context)は、背景や文脈の読み取りが少なく、背景や文脈の共有の少ない状態で言語によるコミュニケーションがされています。(歴史、文化の脈々した流れからの形成物)複数の民族が集まっていることが多く、日本のように共通する歴史、文化の脈々した流れではなく「阿吽の呼吸」、「一を聞いて十を知る」のようなバックグラウンドではありません。
ローコンテクスト文化では、背景や文脈を推測、依存しないで明確にする会話がされるのは自然な流れでしょう。
「ハイコンテクスト(hi-context)」と「ローコンテクスト(hi-context)」は歴史的・文化的な背景により生まれコミュケーションスタイルが異なります。文化です、両者に優劣はありません。文化は時のながれや人の流れに伴い融合しますが、優のよいところは取り入れることです。
あなたが何かを話す時に聞き手に「阿吽の呼吸」、「一を聞いて十を知る」、「概念や抽象語」で話すのではなく、文章化しておくことが必要です。明文化してあれば、無用な混乱やすれ違いを避けながら論理的思考に基づく議論が進められます。

AIに理論的思考による指示、命令するのは人間です。
人間は理論的思考による文章が大事なのです。
AIの知識に甘えない。
知識は有力であり、適切に使えば知識は「力」であるけれども、困ったことに、知識が多くなると、安易な方法に依存し、自分で考えることをしなくなる。それが人間か?
知識があれば、わざわざ自分で考えるまでもない。知識をかりてものごとを処理、解決できる。知識が豊かであるほど思考力が働かない傾向になる。極端なことを言えば、知識の量に反比例して思考力は低下する、と言えるかもしれない。
“理論的に考える力が欲しい······”と思うことありませんか。
理論的に考える力、つまり「理論的思考」の能力を求める理由は人それぞれでしょう。けれども、日常生活でも仕事の面でも、理論的思考の力が発揮できれば、大きなメリットを獲得できます。質の高い情報と疑わしい情報との違いも見きわめられ、有害な・フェイクな情報から自分の身を守りやすくなります。自分から情報を発信するときも、発信内容の「品質保証」ができるようになります。さらに、これができる人が社会の中に増えていけば、情報のクオリティは高まり、コミュニケーションは円滑になり、たくさんの素晴らしいアイデアが生まれ、さまざまな社会的問題の解決に結びつきます。
理論的思考が、専門家ではない多くの人にとって大事なのは、一般人に実用的なメリットがあるからです。
人の定義は未定
 では、人(人間)はどのような生き物であるかについて考えてみます。
では、人(人間)はどのような生き物であるかについて考えてみます。
人とは何かという明確な定義を目にしたことはありませんが人は歴史的視点からその定義をしている。また、大学や公的研究機関における研究職は、ほとんどの分野で「人とは何か」という問いに向けた研究に取り組んでいます。医学は、人を医学的に理解しようとする分野し、法学は、人や人社会を法という側面から理解しようとしています。経済学は、人を経済活動という側面から理解しようとしています。教育学は、人を教育することに関する学問です。工学もその目的は人に役に立つ物を作り出すこととしている。このように、ほとんどの学問は人の定義を求め模索していますが人はまだ進化の途中でもあり、その定義はあまりクリアでなく未定とするほうが適切です。
しかし、一つ明確に人が他の動物と異なる点があります。それは、科学技術によって、その能力を拡張しているという点です。
例えばワクチンである。人が生まれてすぐに、自らが生み出した人工物であるワクチンを体に取り込む。これによって非常に多くのいのちが救われている。また、人は科学技術の力で、快適な家や街をつくって自然の脅威にさらされることを防いでいる。食べ物の多くも、科学技術の力で効率良く、品質に良いもが生産されています。
科学技術で進化する人
すなわち、人は、生物進化のメカニズムである遺伝子の仕組みで、環境に適応し、進化するだけでなく、科学技術によってその能力を拡張しています。科学技術は、人にとっては進化の手段となっています。
そして、この技術による進化は、遺伝子による進化よりも遙かに早く、人は、スマートフォンという技術によって、世界中の誰とでもいつでもどこでも話をすることができるようになった。このような能力を人の進化のメカニズムで獲得するにはどのくらい年月を要したでしょうか。人は、ロケットと宇宙船・宇宙服という放射線を弱点とする人体を強化する技術によって、宇宙を訪問することができるようになった。
500万年前に、人が誕生し、1万年前に農耕が始まった。それ以来、人は技術の力で、その能力を飛躍的に拡張してきたのである。そしてその能力拡張は、近年のAI技術やロボット技術によって、さらに加速しようとしている。
科学技術の発展:
科学技術による人の能力拡張
自動車が発明される以前は、荷物は人や馬などの動物が荷車を引いて運んでいた。しかし、それらの作業は自動車により効率的に行うことができるようになった。また、単なる移動も、自動車によって格段に効率が良くなった。自動車に加えて飛行機が登場し、現代社会では、人は科学技術の力なしでは、生活することが難しくなっている。いずれにしろ、移動するという能力は人にとって特別なものではなく、技術によって置き換えられ、拡張される能力となった。
同じことが近年のコンピューターやAIにもいえる。コンピューターの記憶能力は人を遙かに凌駕する。コンピューターは遙かに多くのことを正確に記憶できるのである。記憶する能力はもはや人にとって特別なものではなく、技術によって置き換えられ、拡張される能力となった。AIも同様である。多くの文献を調べ、取りまとめ、他人から与えられる質問に答えることができる能力も、もはや人にとって特別なものではなくなった。それらの能力を知能と呼ぶなら、知能も人にとって特別なものではなく、AIという技術によって置き換えられ、拡張されていくでしょう。
このようにして、人は様々な能力を技術に置き換え、他の動物とは比較にならない早さで進化している。そして、おそらくは近い将来、人は遺伝子で進化する生物を超えた生命体になる可能性があるのでしょう、私はそう考える一人で、一人ひとりが人間とはの定義をすれば、その努力により『Well-being』に到達します。

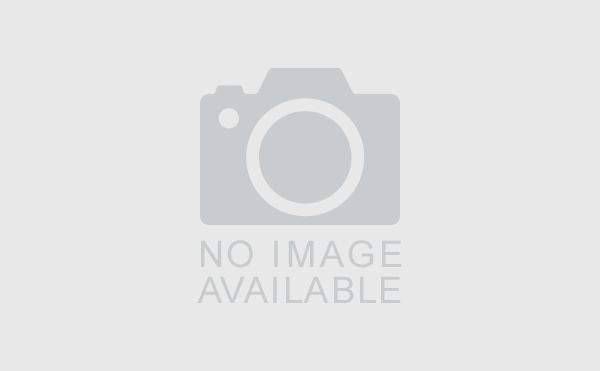

コメントを投稿するにはログインしてください。