組織ビジョン変革(Organization Vision Transformation)
Organization Vision Transformation
Table of Contents(コンテンツ目次)
 ビジョンとは何でしょうか、それは将来の未来像、目指す着地点のこと、ありたい・あるべき姿を明文化したものです。ビジョン(vision)はそもそも「先見」「展望」「構想」を指す言葉です。 またビジネスで使うビジョンそれは一般的に経営目標に近い意味合いを含みますがビジョンには目標とする数値などを入れません。(現在進行中 on-goingの状態に数字目標を入れせん)
ビジョンとは何でしょうか、それは将来の未来像、目指す着地点のこと、ありたい・あるべき姿を明文化したものです。ビジョン(vision)はそもそも「先見」「展望」「構想」を指す言葉です。 またビジネスで使うビジョンそれは一般的に経営目標に近い意味合いを含みますがビジョンには目標とする数値などを入れません。(現在進行中 on-goingの状態に数字目標を入れせん)
「ビジョン」の言い換え表現は、「未来像」「展望」「構想」「青写真」があります。
変革(Transformation)とは?
 組織やプロジェクト全体のビジョンを根本的に変える場合に使います。
組織やプロジェクト全体のビジョンを根本的に変える場合に使います。
例えば、企業のビジョンを「利益追求」から「社会(ステークホルダ)への貢献」に変えるときに使い、変革は、何を、どのように、なぜ進めていくのかを効果的に伝え、これからどのようにビジネスを展開し、どのようなことをビジネスに期待するのか、期待することを明確にします。
それにより、社員、関係者は以下に自問自答をしビジョンを受け入れやすくなります。
ビジョンは、社員・関係者の貢献の方向を示し、組織全体の活動を統合し、社員・関係者の行動を促します。
ビジョンは組織全体の活動を統合し、社員の行動を促すうえで、決定的な意味を持っています。「適切なビジョンがなければ、変革に向けた努力は、ごちゃごちゃで社員が矛盾した時間ばかりを要する烏合の衆になってしまう。結果、誤った方向に進むか、あるいはどこにも行き着かないという事態に陥ってしまう。」
「『顧客志向、サイクルタイム短縮』『組織のリエンジニアリング』などという言葉だけの“ありふれたスローガン”を印刷した掲示物やステッカーを貼るだけのキャンペーンでビジョンを掲げても有害な効果しか出ません、陳腐なスローガンは、社員・従業員、関係者の物笑いのネタになる。そして、冷ややかな笑が意味あるビジョンとなり機能し始めると、根深い冷笑となり、社員・從業員の仕事への取り組み意欲が会社から離れていく。
 つまり経営の基盤としてのビジョンは『社員の努力の方向性を示し、組織全体の活動を統合し、社員の行動を促進』することが必要です。
つまり経営の基盤としてのビジョンは『社員の努力の方向性を示し、組織全体の活動を統合し、社員の行動を促進』することが必要です。
短期的な競争上の理由から変革に乗り出すことはではありません、その証拠にやっとISO標準45001も2027年にはWell-beingが要求事項に採択されます。だから全員参画の上でWell-beingを構築するビジョンが必要です。自分の会社を全員でどこに導いていきたいのか、その行き先をはっきり見据えて理解するステップを踏むことが必要です。
 自分にとってこのビジョンはどのような意味があるのだろうか。
自分にとってこのビジョンはどのような意味があるのだろうか。
(下の質問にお答えください。)
- 自分にとってビジョンはどうだろうか。
- 仲間にとってビジョンはどうだろうか。
- 今いる部署に取ってビジョンはどうだろうか。
- 他に今ビジョンらしきものがあるが、どのような代替案があるのか。
- よりよい代替案はあるのか。
- ビジョンが変わっても、やり方が変わっても、うまく仕事をこなせるだろうか。
- 必要な新しい技能は、どのようにして学ぶのだろうか。
- 個人的な寄与、貢献を払わなければならないのだろうか。
- そうなら、それはどのようなものだろうか。
- 自分は、このビジョン変革を必要だと思っているか。
- 本当に自分たちのとるべき正しい方向を示すビジョンになるのだろうか。
コミュニケーションを行き詰まらないようにする進め方について
 コミュニケーションは身近な話題について雑談することです。その結果、社会システム、会社システムが変わっていくことになります。
コミュニケーションは身近な話題について雑談することです。その結果、社会システム、会社システムが変わっていくことになります。
そこにはネットワークが必要です。コミュニケーションは話している内容が相手に伝わっているかを、インタラクションをして確認しながら進めます。話が一方的になりすぎると私のカナダ国、アメリカの体験では、立ち去る人がいる気がします。インタラクションにより相手に真意が伝わってコミュニケーションの価値が生まれます。そして行動すれば価値は価値を生んでいきます。 何かを考えるとき、理論や形式にとらわれるのではなく、そこに人間的な側面をどんどん入れていくことで、物事はスムーズに進み、組織も活性化します。
とはいうものの、
コミュニケーションには情報が必要です。
さて60%~80%何を意味する数字でしょうか?
働く人の60~80%はビジネスの決断に必要な情報を発見できていないか、または情報があっても自らの決定に活かせていないと考えています。第一線で働く社員の80%は、自分に必要情報は何かが分からず、また入手可能な情報も業務の意思決定に活かすことができないと回答しています。
マネージャーの60%も同じような内容の回答でした。 そして60%~80%の人たちは、役立つ情報はどこかにはあるはずと感じています。でもなかなか勤務時間内で、それは発見できないか、あったとしても限られた時間の中では十分に活用することはできないとの回答でした。
メタ認知と呼ばれる意識プロセス
 「初心者が何か新しいことを始める際には認知的負荷は高くなります。人間にはメタ認知と呼ばれる意識プロセスがあります。
「初心者が何か新しいことを始める際には認知的負荷は高くなります。人間にはメタ認知と呼ばれる意識プロセスがあります。
note:メタ認知とは自分が認知していることを客観的に把握し、制御すること、つまり「認知していることを認知する」ことです。 メタ認知能力をアップできれば、自分自身を冷静に見ることができます。 その結果、高い目標の設定や達成力、問題解決力などを引き上げることができます。
メタは「超えている」の原意。 きっと皆様は初心者ではないと思います。 処理すべきことが増えすぎると、そのすべてを処理することが不可能になります。そこでチームとPro & Con意見を重んじた、議論をして安易に妥協しない議論を避けない職場、忖度をしない職場でコミュニケーションをする。結果、状況からやってくる要求事項を勝手に対処案を決めないで必要な時は議論、ディスカッションして業務処理をしていきます。
また、業務を適切に、実情にあうように設計して、業務の遂行ツールを準備して、全員で与えていきます。そして常に身近な業務などの話題について雑談、相談できるコミュニケーションの場があれば仕事はスマートに進められます。
別の言い方をすれば、「職場内に建設的な対話の場があり、積極的にコミュニケーションが行われている」議論するコミュニケーションは知識・情報の回収を容易にすることができ、目の前に起きている様々なものごとの意味、問題解決を正しく捉えることができます。
非効率なコミュニケーションは仕事を複雑化させる、
仕事を複雑化させるのは、非効率な勝手なコミュニケーションに因があり、人々は今より適切なコミュニケーションをしようと誰もが懸命にかんがえているんだと、勝手に意見も聞かずに「思い込んでいる」ところから生まれています。
 だが実際は、ほとんどの場合、コミュニケーションは原則と規律に欠けていると、それぞれが勝手に「思い込んでいる」方法のコミュニケーションが行われているに過ぎないと言っています。知識的な仕事をするための本当に役立つコミュニケーションの方法を知っている人などはほとんどいないと言っています。 さて、データから見てみましょう。
だが実際は、ほとんどの場合、コミュニケーションは原則と規律に欠けていると、それぞれが勝手に「思い込んでいる」方法のコミュニケーションが行われているに過ぎないと言っています。知識的な仕事をするための本当に役立つコミュニケーションの方法を知っている人などはほとんどいないと言っています。 さて、データから見てみましょう。
どのように感じますか? 多くの会社・組織の75%は『コミュニケーションを、「会社や顧客の利益となる仕事に社員の努力を集中させるため、会社側のメッセージを現場サイドに(一方的に)伝達すること」と定義』しています。これに対し『「仕事に必要な業績ベース、業務ベースの情報を共有し利用すること」と定義』した会社・組織は10%に過ぎなかった。この食い違いについてリーダーたちは「コミュニケーションは経営の仕事で、一般的なコミュニケーションとは違う!」との意見があった。一方、現場からは強い調子で、「全然分かっていない。コミュニケーションですべてを明快にし、どのような意味を持つかを明らかにすることが重要なのだ。そんなことも分からないから、トップマネジメント、リーダーは状況を明快にすることでもなく、ただ組織内の調整や自分が管理できることのみに執心している。」
「何をすべきか」、「それをどのように進めるべきか」
 「何をすべきか」「それをどのように進めるべきか」について、最終決定は、会社が決めたプログラムやプランでもありません。また(IT、AIなどの)技術でもない。
「何をすべきか」「それをどのように進めるべきか」について、最終決定は、会社が決めたプログラムやプランでもありません。また(IT、AIなどの)技術でもない。
決定するのは組織で働く人々です。より良い意思決定を可能とし、会社のビジョンに向かうためにコミュニケーションは「かなめ(要)」です。「かなめ」として存在すべき。
より良いコミュニケーションを行うには、日々の仕事の中で「身近な話題についてコミュニケーションや雑談をする」を実現させる必要があります。シンプリシティは仕事の選択肢が際限のない組織の中で、自分は何をすればいいのかを見出すために、複雑な状況を明快にカンタンにすることです。 「賞賛すべき企業」は明確な目標と目的を持っている。
自らの目標と目的を明確に保つため日夜、努力を続けているLearning companyです。
ビジョンを作り上げる方法
 何か新しいこと、それが大きく、複雑であるとき、私たちが持たなければならないものはビジョンです。ビジョンを持ち進み、今ビジョンがあればまづはそのビジョンを見直してみることです。
何か新しいこと、それが大きく、複雑であるとき、私たちが持たなければならないものはビジョンです。ビジョンを持ち進み、今ビジョンがあればまづはそのビジョンを見直してみることです。
一方ビジョンを作ることは難しく、ずいぶん前ですが社内でビジョンを作らずに外注している会社がありました。ビジョンは一日二日で、できるものではありません。
ビジョンはコミュニケーションするときの身近な話題となるべきです。ビジョンを社員は知らず、会社のHPに載っているだけ。 私たちがビジョンを見直すときや作るときは限られた時間内で対応しなければなりません。
限られた時間内でビジョンの策定
それは、何らかの「仕組み」です。この仕組みが「マネジメント·システム」です。 システムは『Input ->Transformation-> Output』で構成されています。
 たとえば、身近な話題って何でしょうか。これからITに関連する仕事で働く必要のある人はきっと「ITの勉強をどうやってやったらいいでしょうか?」とチームリーダーに聞いてみようかなと思っているでしょう。そのとき、まずチームリーダーはITに関連する次のテーマが仕事職場に入ってくることをすでに知っているのですから「ITにこんな案件が入ってくるんだけど、こんなトレーニングを進めようと考えているけど、どう思いますか?」ということをこちらから聞きに入らなければなりません。
たとえば、身近な話題って何でしょうか。これからITに関連する仕事で働く必要のある人はきっと「ITの勉強をどうやってやったらいいでしょうか?」とチームリーダーに聞いてみようかなと思っているでしょう。そのとき、まずチームリーダーはITに関連する次のテーマが仕事職場に入ってくることをすでに知っているのですから「ITにこんな案件が入ってくるんだけど、こんなトレーニングを進めようと考えているけど、どう思いますか?」ということをこちらから聞きに入らなければなりません。
そして「学んだあとあなたはどんなことをさらに学びたいのですか?」のような個人の思いを聞く必要があります。そのような思いや考えを確認することなく、なんとなくクエスチョン、アドバイスのやり取りをするだけのコミュニケーションでは非効率です。
どんなことでも、何かことを行おうとするときは、ビジョン(思い・想い)を確認し合うことが大事です。そして、熱い気持ちだけの行動は途中でとどまりやすく頓挫しやすい。パッションだけでない、自分自身、職場、組織のマネジメントシステム(マネジメントの仕組み)を使うことです。
ビジョン作成には、二つ知っておいたほうがいいこと
①フォアキャスティング。これは「今はこうである。これまでこういう変化、伸びをしている。このままだとこうなってしまう。過去・現状・未来を基礎とした先を見る、過去を分析はするが、分析ばかりやらない、今から先をみるForecasting的なビジョン構築です。
起点はあくまでも「いま」です。 もう一つは、②バックキャスティングです。いまどのような状況にあるかは考慮せず、まず「どうなりたいか」の未来を考えます。つまり思い、想い、ビジョンを先に作る。そしてそこから現状を見て振り返り、その間を埋めていく、これがBack castingです。 例をあげたITのトレーニングも、「なんとなくITを勉強したい」という、いま持っている気持ちからITの勉強をすると、トレーニングは受けるが、何かむつかしい気がしてとか理由付けして、挫折します。 挫折しないようにするためのツールのいくつかをリストアップしました。 ·メンタリング(継続的指導)コーチング(指導)·クラスルームトレーニング、実践訓練 ·IT(ノート·パソコン、ネットなど) ·スポンサーシップ、チャンピオン ·個々の仕事のための手順・標準のイントラネット情報 ·追加予算 ·人員の追加 ·専用のスペースや場所 ·オフィシャルミーティング、オフサイト·ミーティング ·研究データ ·ベスト·プラクティス ツールと課題をどうリンクさせ提供するかはリーダーが果たすべき責任です。もちろんチームメンバーに問いかけて提供する体系した情報を、適切なッールで適切なタイミングで、正しく使えば社員の仕事を減らし、正しい仕事に集中させることが容易でシンプルになります。 Fore casting、Back castingについては以下の参考をご覧ださい。
コラム:エネルギー政策にも、持続可能な社会にも、「私たちの国はこうなる」というビジョンを持って政策を立案している国は多い。
たとえば中国、アジア環境会議で、中国の代表者が「私たちは50年後の中国をこういう国にしたいと思っている。そのためにいま、この施策を打っている」ということを主張した。
それに対して、日本の代表者は「いま、私たちはこの問題に直面している。それを乗り越えるためにこの施策を打っている」ということを主張した。大局でなく、今を注視して少しづつ先へ先へと進める、中国と日本の戦略的が、バックキャスティングとフォアキャスティングの違いです。
最後に実践行動です。 これまでやってきたこと、慣れていることから、いったいどのようにすれば行動を変革することができるのだろうか?
新しい製品や技術が開発されると新しいものを使う人が出てきます。そして、ビジョンも同じように、「それなら自分もそのビジョンに向かってみよう」と考え行動する人が出てきます。
いくらビジョンがよくても、いくらビジョンの内容に正当性があっても、人はなかなか行動を変え変革することはできません。「どんなに美しい言葉でもそれだけでは伝わらない」と理解して、自分の言葉でビジョンを伝え雑談する人が出てくる。
行動を変革するために、知っておいてほしい方程式
「 ギルマン(ロジャー・ギルマン)の方程式」という考え方です。
ギルマン(ロジャー・ギルマン)の方程式」という考え方です。
・行動の変化が起こるのは極めて単純な考え方であるが、新しい方法とこれまでの方法を比べたとき、新しいやり方には“メリット(得)”がある場合である。しかし、メリットが大きいだけでは、人はなかなか行動を変えない。
・行動を変えると、いろいろな犠牲を伴うからである。お金が余計にかかる、時間がかかる、使い方を学ばなければならない、他人と違うことをしていると気にしなければいけないなどである。そうした犠牲よりも得られるメリットが大きいときに、人は行動を変える。 例をあげよう。これまでクルマといえば、ガソリン車であった。そこに新しく省エネルギーのハイブリッド車が出てきた。このハイブリッド車のほうが、地球温暖化に対しても、燃費の点でもよいのは明らかである。販売店もその点を特に強調している。ガソリン車に比べると絶対メリットがあるはずである。でもなかなか買いません、ナゼでしょうか。
買いが始まるにま、井戸端会議ネットワークで生まれる口コミ、熊さんと八さんの雑談からはじまる口コミが必要です。
コミュニケーションは話している内容が相手に伝わっているか確認しながら進める、
ハイコンテクストの日本のように丁寧な相手のことを汲んでいない一方的な話になりすぎると、参加者はただ聞くだけです。相手に真意が伝わってこそコミュニケーションに“「Aha(アハ)」という感嘆詞と体験が組み合わさって、「なるほど!」や「わかった!」といったひらめきや理解の瞬間によりを表すコミュニケーションの価値が生まれます。
何か考えるとき、理論や形式にとらわれ過ぎないで、そこに人間的な側面(喜怒哀楽)さらに思考、行動、信念、価値観など内面的なことをコミュニケーションすること。
組織開発においては、人間的な側面をマネジメントすることが、職場の雰囲気や人間関係の改善になり、業績の向上につながります。そして、結果、自然に物事はスムーズに進み、組織も活性化するようになってきます。
全員参加で進むためには、異質なものを排除せず、多様性を受け入れる,
ポイント1: 自分も多様性の一部である
多様性の尊重には、「私は、私と違うあなたを尊敬します」という人がいますが、これは自分を多様性の外に置いて、さらに自分自身を「基準」にして相手との違いを見ています。” 比較をすること、そして素直に受け入れない、これはまずいな” と私も自分自身が相手を受け入れる前に比較することを反省します。
多樣性には、「自分も多様性の一部分だ、相手も多様性の一部だ」と一緒の枠にいるチーム員と受け入れることが重要です。
ポイント2: 事実と解釈・意見を混同しない。自分と異なる世界や人々を理解するときには、事実と解釈を分けることが必要です。
なぜなら、事実を解釈する際に、自分の経験をあてはめて解釈してしまうからです。解釈は、自分の解釈だけではなく他人の考え、意見、事実を聞くこと。
ポイント3:フラットでオープンである
階層やポジションは単なる「役割の違い」であって、コミュニケーションの場にはPsychological Safety(心理的安全性)を持ち込み、上下関係の役割を持ち込まないこと。するといつかはWell-being。
まとめ
 – ビジョンは 将来の理想像や目指すべき方向性を指し、社員や関係者の行動を統合・促進する役割を持っています。
– ビジョンは 将来の理想像や目指すべき方向性を指し、社員や関係者の行動を統合・促進する役割を持っています。
- 変革(トランスフォーメーション)は、組織のビジョンを大きく変える過程で、「何をどのように、なぜ進めるか」を明確化することを含んでいます。
-
効果的なコミュニケーション とは、一方通行ではなくインタラクションを重視し、人間的側面(信念・価値観)を取り入れた対話が大切です。
-
意思決定と情報共有の課題: 多くの社員が必要な情報を発見できず、その情報を業務に活かせていないことが上がっています。
 – ビジョン構築の手法:「フォアキャスティング」と「バックキャスティング」という異なるアプローチがあり、どちらもビジョンを明確にするプロセスを含含んでいます。
– ビジョン構築の手法:「フォアキャスティング」と「バックキャスティング」という異なるアプローチがあり、どちらもビジョンを明確にするプロセスを含含んでいます。
- 行動の変革には、犠牲とメリットを比較し、メリットが明確に勝る場合に変化が促されます。
-
多様性の尊重や心理的安全性が重要であり、建設的な議論を通じて社員全員が参加しやすい環境を作ることが重要です。

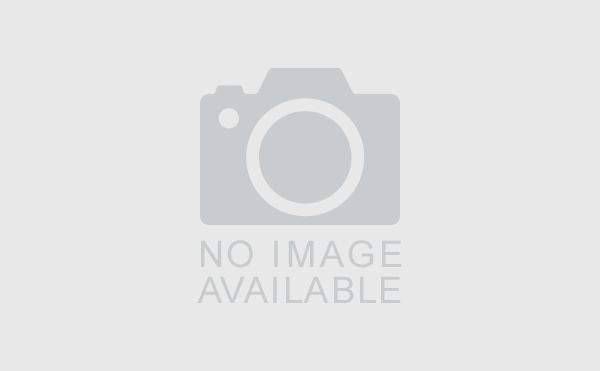

コメントを投稿するにはログインしてください。