Part1 Cognitive tools to build a safe workplace: ISO 31000 & ISO 45001

コグニティブシステム
Table of Contents(コンテンツ目次)
コグニティブシステムというのは、認知的なタスクを実行するためのシステムのことです。認知タスク分析とは,現実下におけ る人間の行動,振る舞いのもとである背後にある知識の活用,思考プ ロセス,態度といった認知的側面に焦点をあて,それら をフィールド観察やプロセス追跡,インタビューやアン ケート等によって抽出・整理することです。
具体的には「知覚情報に対して知的処理により、行動に変える」それがコグニティブシステムです。このシステムの構成自体は一般的な入力装置、変換装置、出力装置と大きくは変わりません。さらにえば人間の知的活動に似ています。脳の動き、右脳左脳……人間も五感で知覚した情報をベースに脳が判断・解釈を行い、それに対して行動を決定するという入出力(脳は処理)装置の側面を持っています。

人間やコグニティブシステム
人間やコグニティブシステムは、一般的なコンピュータとは違います。システムに入ってくる知覚情報データは、構造化されていないものが含まれ、それらのデータに対して認知・認識をし続けなければならない高度な知的処理を行います。
AI(上図): コグニティブシステム
AIは個々の技術要素にディープラーニング(機会学習)に近い先進的な技術が含まれています。コグニティブシステムにはディープラーニングがないとしても、システムで非構造化データなどの幅広い情報の処理をします。
その一方で、知覚・行動・コミュニケーションのプロセスを伴わない単純なBOTのような場合は、コグニティブシステムとは呼びません。現在、知覚や情報解釈を伴わないことを「認知」と呼ぶかどうかは微妙だからです。
AIと呼ぶ場合、そのシステムの中で一定レベルの高度な知的技術を使います。BOTのように知覚・行動・コミュニケーションを伴わないが知的技術を使っていればAIとして扱います。しかし、コグニティブシステムはあまりそうではありません。
たとえば、蓄積されたデータベースを元に高度な論文を生成し続けるAIというのは十分にありますが、人間や環境とのやり取り・インタラクションが並走しない場合、それが知的なシステムでも、それはコグニティブシステムとは呼ばれないということ。
工場安全におけるコグニティブシステムの活用事例として、
AIを活用した異常検知システムがあります。
例えば、製造ラインでの異常な動作や機器の故障をAIがリアルタイムで検知し、作業者に警告を発するシステムがあります。これにより、事故の未然防止や迅速な対応が可能となり、労働災害の削減に寄与します。(今までもこのような装置・システムは多くありますが、これからはどんどん進化するでしょう。)
また、ドローンを活用した安全監視 も注目されています。
ドローンが工場内を飛行し、監視カメラで異常を検出したり、危険物の存在を確認したりすることで、従来の人間がする安全巡回に比べて効率的かつ安全に監視が行えます。
これらの技術は、社員の安全を確保しつつ、生産性の向上にも寄与します。安全工学やエンジニアリング工学に興味深々ね!他にも知っている方いますね、教えてください。
安全な職場の構築:ISO 31000およびISO 45001の活用
人が関与している企業にとって、従業員の安全と健康を確保することは最優先事項です。
ISO 31000とISO 45001は、リスク管理と職場の安全に関する国際的に認められた基準です。この基準は安全な職場環境の構築のフレームワークとして活用できます。
ISO(国際標準化機構)のガイドライン、ISO規格は25000以上あります。ここは安全な職場を構築のための2つを使い、安全な安心できる職場の実現についての要点を説明します。
ISO 31000とは?
規格のISO 31000は、リスク管理のためのガイドラインを提供しています。リスクの特定、評価、管理、監視のプロセスを構築し、組織の全体的なパフォーマンスと持続可能性を向上に向けています。
主なポイント:
1. リスク特定と評価: 潜在的なリスクを洗い出し、その影響と発生確率を評価。
2. リスク管理策の策定: リスクを最小限に抑えるための具体的な管理策を策定。
3. モニタリングとレビュー: リスク管理の効果を定期的にモニタリング、改善策の実施。
ISO 45001とは?
ISO 45001規格は、職場の安全衛生マネジメントシステムの規格です。この規格は、労働者の健康と安全を保護するためのフレームワークを提供、事故や疾病の防止が焦点です。
主なポイント:
1. リーダーシップと労働者の参加: トップマネジメントのコミットメントと労働者の積極的な参加が求められます。
2. リスクおよび機会の評価: 安全衛生リスクと機会を評価し、適切な対応策を講じます。
3. 継続的改善: 安全衛生パフォーマンスの継続的な改善を目指します。

 NOTE; この先、ISO 31000とISO 45001が安全な職場を構築はPart2をご覧ください。
NOTE; この先、ISO 31000とISO 45001が安全な職場を構築はPart2をご覧ください。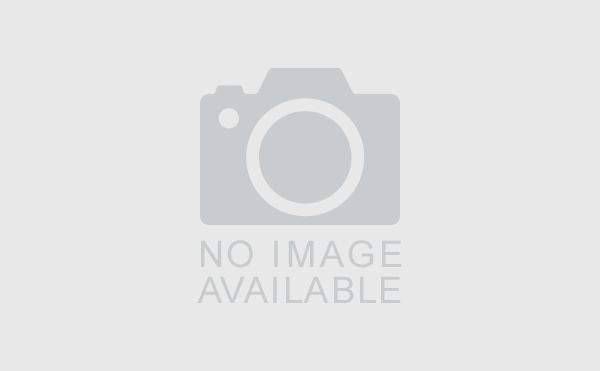
コメントを投稿するにはログインしてください。