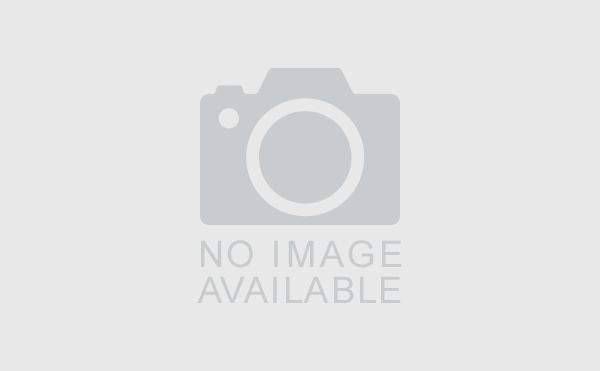Self-learning from a programming development perspective
仕事を進める前の自己学習で注意すること
Table of Contents(コンテンツ目次)
プログラミング開発的な視点で考える
学習方法をプログラミング開発思考で説明します。
学習の全体像をInput(データを入力)とOutput (出力)の視点で捉えます。プログラミングには構成する2つの要素 「アルゴリズム(出力までの処理をするロジック・ストーリー)」と「データ」があります。ポイントその1:InputとOutputで考えよう
何を学ぶのか目的を明確にし、データを Input(入力)します、そして何を得るのか、Output(出力)するのかを考えます。 教材はこれだけでいいのか、他の教材はいらないかをデータとして考えます。データは今までの学んだテキスト、メモ書き、本に書き込んだメモ、ハイライトペンのあと、本の耳オリ(Dog-eared) もデータにつながります。 Output(出力)は自学用として、さらにチームの勉強用をInputに入れて考えれば最高です。ポイントその2:プログラミングとはアルゴリズムとデータできまる
プログラミングとは目的を達成のために①アルゴリズム(処理)を設計し、②その過程で必要なデータを扱うことです。ポイントその3:アルゴリズムとは?(出力までの処理をするロジック・ストーリー)
アルゴリズムとは、目的達成のためのロジックとストーリーで、①順次実行 ②繰り返し(ループ)③条件分岐によって作ります。3つの制御構造です。 この3つでJAXAの宇宙開発の理論は(資金や人材は成り立っていないかも)成り立っています。
この3つでJAXAの宇宙開発の理論は(資金や人材は成り立っていないかも)成り立っています。
ポイントその4:アルゴリズムの3つの構成要素
ポイントその3と重複しますが、①順次実行 ②(条件)分岐 ③繰り返し、学習だけでなく日常生活でも、①②③は解説不要であまり気が付かないでしょうが、日常の行動となって習慣化しています。 週末に公園に出かけたとき、順番に順次行動を立て、さて電車は? JR、私鉄、地下鉄、バス、どういう経路? かかる時間は? 交通費は?と「アルゴリズム(出力までの処理をするロジック・ストーリー)」と「データ」を使っていますね、” 駅で”しまったPASMOを忘れた、でもSUICA持っているからいいか”と、①②③を繰り返しています。ポイントその5:データを扱う3つの道具 変数·関数·配列
「データの扱い」のための3つの道具、①変数 ②関数③配列を説明します。 ①変数は、 データの入れ物、教材はPCのどのファイルに保存しているか、またはどのUSB、どのSSDか、または本棚のどこか? ②関数は、 決まった処理をするときの道具です。コンピュータはどれ、使うソフトは、そしてその結果何が出る、関数はデータを変換するものです。 ③配列は、 データを入れておくデータベースです。EXCELの配列をイメージください(行と列ですね)。データベースでは行のことをRECORD、配列のことをFIELDと呼びます。ポイントその6:データベースを扱う4つの方法。
4つは、参照·新規保存·上書き保存·削除。 ・参照できる、データーベースを探して取り出し(取得)、 ・新規保存ができる、新しい資料を新規保存することが例です。 ・上書き保存はデータを取り出し、編集、修正したら戻して上書き(保存)する。 ・削除できます。ここまでのおさらい。
目的達成のためのロジックとストーリーで、①順次実行 ②繰り返し(ループ)③条件分岐、3つの制御構造です。 順次処理とは、処理する順番に記述されているプログラム構造のことで、単純に、上から下に処理が流れていくシンプルな構造のこと
反復(繰り返し)構造とは、条件を満たしている間、または条件を満たすまで処理を繰り返すプログラム構造のこと
(ループ構造の中にさらにループ構造がある二重ループ構造もあります)
分岐構造とは、条件によって処理内容が分かれるプログラム構造のこと
フローチャートを書くとプログラムの全体像が明確になり、設計漏れやバグを減らすことができます。学習プログラムの質が上がります。
以下が、一般的なプログラム開発のステップです。プロジェクトの規模や要件によっては、さらに細部のステップが必要になることも多くあります。サブシステムとのやり取りが必要になります。
順次処理とは、処理する順番に記述されているプログラム構造のことで、単純に、上から下に処理が流れていくシンプルな構造のこと
反復(繰り返し)構造とは、条件を満たしている間、または条件を満たすまで処理を繰り返すプログラム構造のこと
(ループ構造の中にさらにループ構造がある二重ループ構造もあります)
分岐構造とは、条件によって処理内容が分かれるプログラム構造のこと
フローチャートを書くとプログラムの全体像が明確になり、設計漏れやバグを減らすことができます。学習プログラムの質が上がります。
以下が、一般的なプログラム開発のステップです。プロジェクトの規模や要件によっては、さらに細部のステップが必要になることも多くあります。サブシステムとのやり取りが必要になります。
|