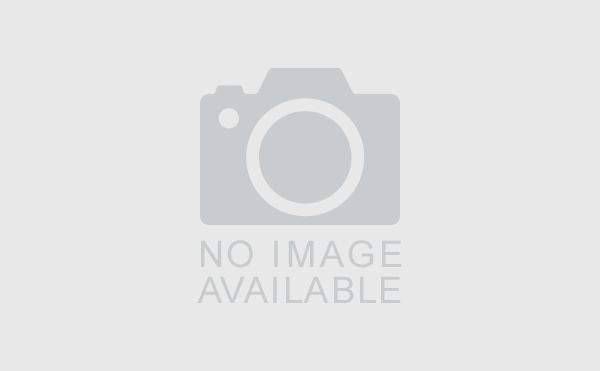Turn a blind eye to the falsified data. 見てみぬふり
 井の中の蛙、ゆでガエル、蛸壺のタコ、見ざる、聞かざる、言わざる – 現場でfalsified改竄を見ても気が付かぬ、気が付いても見ぬふりをする。Turn a blind eye to the falsified data. こんな課題に立ち向かうにはどうすればいいのでしょうか?
井の中の蛙、ゆでガエル、蛸壺のタコ、見ざる、聞かざる、言わざる – 現場でfalsified改竄を見ても気が付かぬ、気が付いても見ぬふりをする。Turn a blind eye to the falsified data. こんな課題に立ち向かうにはどうすればいいのでしょうか?
問題解決にチャレンジするため参考になること
Table of Contents(コンテンツ目次)
井の中の蛙、ゆでガエル、蛸壺のタコ、見ざる、聞かざる、言わざる – 現場でfalsified改竄を見ても気が付かぬ、気が付いても見ぬふりをする。Turn a blind eye to the falsified data. こんな課題に立ち向かうにはどうすればいいのでしょうか?
見てみぬふりの課題解決に立ち向かう環境を作る
この問いに答えるには、まず見てみぬふりの課題は私が存在する組織にあるのだろうか?それは何か、きっとそれは自分の組織にとって重要だろうが、解決が面倒だったり難しかったりすると無視したり避けたりする。例えば、そこに落ちているごみについて、”気づいたら拾ってゴミ箱へ”とガミガミと文句をいっているように感じられるのではと思うということはできない。ダダひたすら一人で捨て続ける。言い続けない。
課題解決に立ち向かうにはどうすれば、課題に目を向け、分析し、行動する能力や意欲を育む手段ってあるのだろうか。
周りのことを考える人は、どのように立ち向かうか、その立ち向かう前に現在の状況を立ち止まり確認することをしているのでしょうか?
現在の状況を確認することは、自分の持っている価値観や行動パターンによります。さらに自分の育ってきた環境や背景、自分の持っている価値観は、情報はどこから得ているか、その情報源やメディアからの影響の程度?自己分析していつかなと自問。さらに、自分以外の人はどのような価値観や行動・思考パターンを持っているか、他者にまで、他人の分析まで手を広げるのか?
コミュニケーションから得るもの
”ゆでガエル状態が気になったんけど、あなたはどうなの、教えてくれない” のようにコミュニケーションをする。自分と他者の立場や視点を理解し、相互に対話することで、多様な知識や意見を得ることができるだろう。
でも、
コミュニケーションからだけでは解決には至らない
知識や意見をもとに、具体的な解決策や行動計画を作るには、どうすればいいのだろうか、さらに論理に考えるにはどうすればいいのだろうか。
論理的にするためには、事実と仮説を区別し、根拠や論証を用いて正しく推論すること書いてある書物が多い。さらに創造的にするには、既存の枠組みや常識にとらわれず、新しいアイデアや方法を発想することと書いてある。今までに得られた知識や経験を活用することではダメだと思えてします。
こんな問答を繰り返しやっと寒い時期がやってきてしまった。また自問しながらいると暑い暑い季節がすぐやってくる、その前に、
問題解決にチャレンジするために得たこと
1.基礎的・基本的な知識や技能を確実に身に付ける「リ・トレーニング」をすること。「確かな知力の基礎力」を養う。知識や技能だけではなく、自ら学び自ら考える力・思考力・判断力・表現力・コミュニケーション力などを学ぶ。
2.自分自身や他者・チームメンバー・社会や自然との関わりを見直すこと。これが今いる組織、チームメンバーの動きに目を向けることにつながってくる。
小さい時の教育から得たのは学ぶ姿勢や技能を仲間と一緒に培った。組織は「持続可能な組織の開発」を掲げ社会の問題の解決につながりを持ち、世界的な視野を持ち社の価値を高める一員を私に求めている。
エンジニアとして、考えた事
「学びは物事の基本を極めること。量子コンピューターがこの先実用化されても使っているのはごく狭い範囲。まだまだチューリングマシンとかノイマン型コンピューターと言われた世界から抜け出ることはない。アルゴリズム、データ構造、コンパイラーといったコンピューターの基本にもう一度触れてみる」
基本は重要です、地球上は「PCの安全保障も大事。コンピューターもプログラムもほとんど海外からの輸入品というより瞬時にインストール、しかも内容はブラックボックス、自分ではコントロールできなくなる。でもシステムを自力で用意することはできない。
「海外でITの仕事をする人はコンピューターサイエンスを学んでいる。ところが日本では大学の学びとは関係なく、道具として使うITの仕事についている人が多い」、日本のものつくりは猿真似、Copy catと言われた。
海外企業には基本を学ぶシステムがある。大学が大学のビジネスとして、企業向けの教育コースを提供し、そこで基本から教え、企業はそれを社内に取り入れている、人財育成(人材ではなく人財)。日本の企業の社内教育は即戦力を目指すあまり、猿真似、Copy catとマダマダ近視眼的。社員は自分の基礎を見直す機会を逃している。
ServiceNow Strategic Portfolio Management (SPM)
出典:servicenow.com
『あるべき姿』にどこまで近づき、その結果どんな成果を出すことができたかの達成状況を、数値(例%)で把握し、全体だけでなく、個別改善の達成状況を可視化する。『改善努力がどこまで実を結んでいるのかが分かりやすい』

have a safe and nice day.
Design Safety System